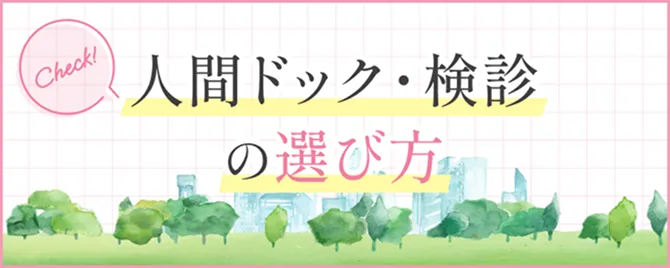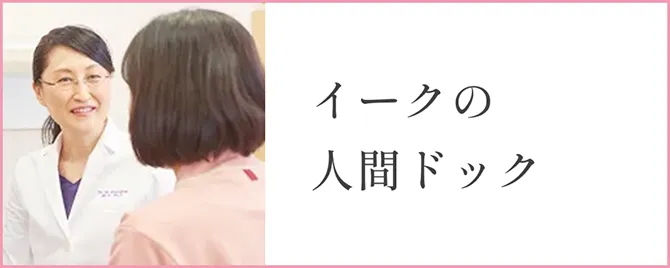子宮にまつわる病気や症状
子宮の病気の中には自覚症状がほとんどなく進行するものもあるため、定期的な健診で状態を確認することがとても大切です。
以下の記事を参考にしつつ、気になることや不安なことがあれば、ぜひご相談ください。
子宮筋腫(しきゅうきんしゅ)
子宮筋腫は、子宮にできる良性の腫瘍のことです。発生頻度は30歳以上の女性で20~30%と言われています。
一般的に子宮筋腫は症状を自覚しにくく、自分では気づかないまま大きくなっていることがしばしばあります。また、位置によっては不妊や流産のリスクが高まったり、月経の出血量が異常に多くなりひどい貧血症状を起こすこともあるため、良性の疾患とはいえ経過観察が必要です。
毎年の職場や自治体の子宮頸がん検診などで婦人科にかかる時は可能であれば「経腟超音波検査」も同時に受診いただき、早期発見、経過観察の機会を作っていただくことをおすすめします。
子宮内膜症(しきゅうないまくしょう)
子宮内膜という組織が、子宮の外で増える病気で、月経困難症や不妊の原因となることがあります。本来、子宮内膜は子宮の内側にあり、卵巣から分泌されるエストロゲンによって増殖し、妊娠する準備をしています。妊娠しなければ、月に1回子宮から剥がれおちて出血し、月経となりますが、子宮以外の場所、たとえば卵巣や腹膜で増殖すると、卵巣、卵管や腸が癒着したり、卵巣内にのう腫ができます。
子宮肉腫(しきゅうにくしゅ)
子宮肉腫は、子宮の筋肉や間質と呼ばれる組織などに発生するがんのことです。子宮肉腫特有の症状はなく、腹痛や、こぶを触れるような感覚(腫瘤)、臓器が圧迫されることによる頻尿など、子宮筋腫と共通した点が多いです。超音波画像診断など、通常の婦人科検査や症状の観察で子宮筋腫と子宮肉腫を区別することはできないため、MRI検査や病理診断の検討が必要です。
※ 転移等で命取りになりかねないものを一般的には「がん」または「悪性腫瘍」といいます。これには「がん」と「肉腫」の2種類の呼び方があり、皮膚や臓器の表面から発生してくるものを「がん」、表面よりなかの組織(骨、筋肉など)から発生してくるものを「肉腫」と呼びます。
子宮頸がん(しきゅうけいがん)
「子宮頸がん」とは、子宮頸部(子宮の入口)にできるがんのことです。原因は、HPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスに持続的に感染することだと考えられており、一般的には性交渉でHPVに感染するため、多くの女性が一生に一度は感染すると言われます。
HPVに感染しても、通常は自分の免疫力で自然に排除されます。しかし、自然に排除されず感染状態が長期間続いた場合、子宮頸部の細胞に異型がみられるようになります。この時点ではがんではありませんが、この状態が持続すると、一部子宮頸がんに進行するとされています。
子宮体がん(しきゅうたいがん)
「子宮体がん」は、子宮の体部(子宮の奥)にできるがんです。子宮内膜がんとも呼ばれます。多くはエストロゲンが関与するタイプであり、発症年齢は閉経前後の40代後半から増加して50~60代の女性に多くみられます。不正出血や褐色のおりものなどが初期症状として現れることがあります。通常、婦人科がん検診では「子宮頸がん検診」を実施しており、体がん検診はしていません。症状がある場合には婦人科を受診して検査をするようにしましょう。
卵巣腫瘍(らんそうしゅよう)
卵巣にできた腫瘍を卵巣腫瘍といいます。卵巣は正常な場合で2〜3cmほどの大きさです。それが7〜8cm大にまで腫れても痛みはなく自覚できることはほとんどありません。検査以外に発見の機会がないため卵巣は「沈黙の臓器」と言われています。ただし腫れた卵巣が根もとからねじれ(茎捻転)をおこすと、急な腹痛や吐き気などの激しい症状がでます。
そのため、経腟超音波検査をきっかけに卵巣腫瘍が確認された場合、イーク丸の内・表参道・有楽町・渋谷では、サイズが小さいうちは婦人科外来で経過を観察(※)し、6cm大になったら手術を視野に当院の提携医療機関やご希望の医療機関での診療をおすすめしています。
卵巣腫瘍は若い方でも発症することがある病気ですが、自覚症状を伴わないことが多いため、症状が無くても1年に1回の婦人科超音波検査がおすすめです。
※婦人科外来での経過観察について
通常、卵巣は排卵の時期になると腫れる傾向があります。腫れ具合によっては、卵巣の異常による腫れなのか、排卵期による腫れなのかを区別する必要があります。そのため経過観察でお越しいただく方には、月経の終わりかけの時期(目安:月経開始日から4日目以降10日目以内)にご来院いただくことをおすすめします。経血が残っていても問題ありません。
よく読まれている記事
-
乳がん検診の結果が「要精密検査」だった方へ25.09.17 最終更新
-
子宮頸がん検査の結果が「要精密検査」だった方へ25.08.20 最終更新
-
乳腺超音波(エコー)検査って何?25.09.11 最終更新
-
乳腺科:乳房・乳がんに関するよくある質問25.09.11 最終更新
-
乳房にまつわる病気や症状25.09.09 最終更新
-
マンモグラフィ検査って何?25.09.11 最終更新
-
イークの乳がん検診は他と何が違うの?25.11.20 最終更新
-
乳がん検査の選び方25.09.11 最終更新
-
子宮にまつわる病気や症状25.08.20 最終更新
-
子宮頸がん検査って何?25.08.20 最終更新